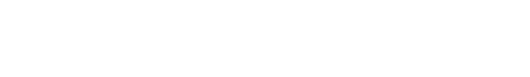訪問者別
大学について
受験生特設サイト
入試情報
進路・就職
キャリア開発総合学科
製菓衛生師養成課程
保育学科
オープンキャンパス
キャンパスライフ
イベント・公開講座
library
図書館
聖和学園短期大学
三浦光哉|アセスメントをフィードバックし自己理解を促すことによる不登校改善
著者
三浦光哉
題名
アセスメントをフィードバックし自己理解を促すことによる不登校改善
著者(ローマ字)
MIURA Kouya
題名(英語)
Improving School Refusal by Providing Feedback on Assessments and
要約
本研究の目的は、小学校3年生から3年間継続している不登校児童(小学校6年生、ADHD+ASD診断)への不登校改善である。その手法においては、心理教育アセスメントであるKABC-Ⅱ検査を実施し、そして、その検査結果と指導方針を本人・保護者にフィードバックして不登校改善のための会議(本人参加型不登校改善会議)の中で具体策を示し、本人の自己理解を促しながら再登校できるような学習環境を整えていくようにした。その結果、本人・保護者は、障害特性(気質)を理解し、また、具体策である、①一斉指導における配慮、②放課後等を使った学習空白の補充、③本人参加型不登校改善会議の取り決めの実施、④母親との連携強化、⑤中学進学後の在籍変更などを受け入れながら実行していき、小学校卒業間際に不登校が改善された。不登校改善のためには、自己の障害や気質(特性)の理解とともに、自己決定力の重要性も指摘された。
キーワード
不登校、本人参加型不登校改善会議、KABC-Ⅱ
ページ
1-10
本文を見る
齋藤美香|老人クラブ設立の歴史的変遷-米倉老人クラブ先覚者・菱木貞俊の取り組みに焦点をあてて-
著者
齋藤美香
題名
老人クラブ設立の歴史的変遷-米倉老人クラブ先覚者・菱木貞俊の取り組みに焦点をあてて-
著者(ローマ字)
SAITO Mika
題名(英語)
Historical changes in the establishment of senior citizens' clubs
要約
本研究では、老人クラブの発祥の地とされている千葉県八日市場町(現:千葉県匝瑳市八日市場)の「米倉老人クラブ」の先覚者である菱木貞俊(以下、菱木と略す)が取り組んだ、老人クラブの設立経緯を明らかにすることを目的とした。菱木が寄稿した記事や同県老人クラブ関係者から収集した資料等から、菱木は戦前から高齢者福祉に問題意識をもち、高齢者に対する独自の支援を行っており、戦前の「老人たちの集い」から戦後の「米倉老人クラブ」へ発展させた。「米倉老人クラブ」創立から約32年間にわたり、つねに地域の老人の言葉に耳を傾け、千葉県内の老人クラブの普及や老人クラブ活動に関する指導など当時の老人福祉の発展に寄与したことが明らかになった。
キーワード
老人クラブ、菱木貞俊、地域福祉、高齢者福祉
ページ
11-19
本文を見る
永野篤|簿記・会計教育における体験学習の新手法 ~仮想企業によるアクティブ・ラーニングの実践~
著者
永野篤
題名
簿記・会計教育における体験学習の新手法 ~仮想企業によるアクティブ・ラーニングの実践~
著者(ローマ字)
NAGANO Atsushi
題名(英語)
A New Approach to Experiential Learning in Bookkeeping and Accounting Education:
要約
簿記・会計教育の苦手意識克服を目的に、仮想企業を用いた体験型学習を導入。学生は架空の経営を体験しながら現金取引を中心に学び、楽しさと理解を実感。現金の動きを基軸にしたシンプルな仕訳法と具体例の提示が効果を上げ、学習意欲の向上が確認された。
キーワード
体験学習、仮想企業、簿記教育、現金基軸、アクティブ・ラーニング
ページ
21-30
本文を見る
永野篤|サービスマーケティングの発想から学生ニーズをくみ取り自発的な学習を促進する英語教育の取り組み
著者
永野篤
題名
サービスマーケティングの発想から学生ニーズをくみ取り自発的な学習を促進する英語教育の取り組み
著者(ローマ字)
NAGANO Atsushi
題名(英語)
Promoting Self-Motivated Learning in English Education by Capturing Student Needs from a Service Marketing Perspective:
要約
本研究は、サービスマーケティングの視点から英語教育を再構築し、学生の感動体験を通じた自発的学習を促す試みである。シェイクスピアのソネットを中心に、映画視聴や音読を交えた授業で、英語への興味や理解を深めた。学生のニーズに応じた柔軟な授業設計により、学びの喜びを引き出し、教育の質向上に寄与する可能性を示した。
キーワード
サービスマーケティング、インストラクショナルデザイン、英語教育、感動体験、シェイクスピア
ページ
31-37
本文を見る
堀良平|若者の地元定着と在学時におけるキャリア意識の変化の関連性について
著者
堀良平
題名
若者の地元定着と在学時におけるキャリア意識の変化の関連性について
著者(ローマ字)
HORI RYOHEI
題名(英語)
The relationship between young people's local settlement and changes in career consciousness during school
要約
仙台市内にあるA短期大学においてジェネリックスキルやキャリア意識の変化を分析し、他道県と異なる傾向があるといえる宮城県において、地元定着をする若者とそうではない若者の傾向を明らかにすることを狙いとした。結果として地元に定着する学生は前向きに検討はしているもの、現実的な可能性として地元を選択し、その枠の中で選択している可能性を示唆し、移動する学生に関しては地元にこだわらない志向があるものの、定着型とは異なり、後ろ向きな進路選択をしている可能性が考えられる。
キーワード
地元定着、キャリア意識、PROG、地域移動
ページ
39-48
本文を見る
丸山穣|1 H NMR による日本酒(清酒)の成分分析の試み 〜特徴的成分と含量バランスが一度にわかる
著者
丸山穣
題名
1 H NMR による日本酒(清酒)の成分分析の試み 〜特徴的成分と含量バランスが一度にわかる
著者(ローマ字)
MARUYAMA Yutaka
題名(英語)
Attempt to Analyze the Composition of Japanese Sake by 1H NMR Spectroscopy :
要約
日本酒の酒造りは古くから日本に根ざしてきた食文化の一つであり、その技術は伝統的に磨かれ各地で発展し、日本酒は日本の文化で不可欠な役割を果たしている。米、米麹、水、という比較的シンプルな原料から技巧を駆使し、微生物を制御して多彩な味わいの日本酒を醸す。醸造の過程で多くの成分が生成され、その成分のバランスで酒の個性がきまる。著者は核磁気共鳴装置を用いて、混合物のまま測定し、含まれる成分の構成比を得て、多変量解析により、試料の個性を官能試験と同じようにグループ分けできることを以前報告した。今回は、試料の個性を特徴付ける各成分のシグナルが、具体的にどのようにスペクトルに現れるか解析を試み、本手法は効果的な解析手法であることを明らかにした。
キーワード
NMR、日本酒、清酒、核磁気共鳴分光法、オリゴ糖
ページ
49-58
本文を見る
山本信|保育学生の実習における情動喚起に関する研究:喚起場面と情動知能との関連に着目して
著者
山本信
題名
保育学生の実習における情動喚起に関する研究:喚起場面と情動知能との関連に着目して
著者(ローマ字)
YAMAMOTO Makoto
題名(英語)
Emotional Arousal in Early Childhood Education and Care Practice: Relationship between Arousing Situations and Emotional Intelligence.
要約
本研究では、実習中における保育学生の情動喚起場面に着目し、強い情動が喚起する場面が情動知能の高さによって異なるかどうかを検証することを目的とし、
キーワード
保育者養成、実習、情動喚起場面、情動知能、内省
ページ
59-72
本文を見る
上村裕樹・君島智子・宮本美和子・金野麻衣・小森谷一朗・後藤さくら・大曽根学|教育実習評価表からみる教育実習学内指導の課題(2)
著者
上村裕樹・君島智子・宮本美和子・金野麻衣・小森谷一朗・後藤さくら・大曽根学
題名
教育実習評価表からみる教育実習学内指導の課題(2)
著者(ローマ字)
UEMURA Hiroki, KIMIJIMA Tomoko, MIYAMOTO Miwako, KONNO Mai, KOMORIYA Ichiro, GTO Sakura, OSONE Gaku
題名(英語)
Issues in on-campus teaching practice as seen from the teaching practice evaluation table (2)
要約
幼稚園教諭養成における授業評価と実習評価の妥当性を検証し、教育の質の保障と学生の学びの向上を目指した。その分析の結果、実習評価は前年度と大きな差異が見られず安定している一方、GPAと実習評価の相関も弱く示された。これは、学力だけでなく、実習における多様な要素が評価に関与することが示唆された。評価基準の精緻化、多様な評価方法の導入、学力以外の要因分析、質的研究との統合など、より多角的な視点からの評価による効果的な養成を目指していきたい。
キーワード
実習評価妥当性、教育実習、質の向上、実習評価、GPA
ページ
73-81
本文を見る
小森谷一朗、金野麻衣、岩淵摂子|保育者養成における評価に関する試み
著者
小森谷一朗、金野麻衣、岩淵摂子
題名
保育者養成における評価に関する試み
著者(ローマ字)
KOMORIYA Ichiro, KONNO Mai ,IWABUCHI Setsuko
題名(英語)
Attempts at assessment in childcare worker training
要約
保育者養成において、行事を踏まえた一連の保育活動を構想しカリキュラム・デザインを構築することをねらいとして授業実践に取り組んだ。事前の環境構成と事後の模擬保育についてのピア評価及び自己評価に着目し分析を行った結果、子どもの環境への関わりについて理解すること、保育を想像する力が求められること、また、事前に評価の観点についての共通理解を測ること、評価の重要性を認識させることの必要性が示唆された。
キーワード
ピア評価、自己評価、評価の観点、カリキュラム・デザイン、環境構成、模擬保育
ページ
83-89
本文を見る
永野篤|図書館員としてのキャリア構築支援への課題
著者
永野篤
題名
図書館員としてのキャリア構築支援への課題
著者(ローマ字)
NAGANO Atsushi
題名(英語)
Challenges in Supporting Career Development as Librarians: The Significance and Motivation of Obtaining Librarian Qualifications at Junior Colleges
要約
図書館司書資格取得後の非正規雇用の現実を踏まえ、卒業生・在校生を対象に調査を実施。司書職に対する動機や課題、キャリア観の違いを明らかにし、大学側の支援策として多様なキャリアパスの提示や非正規雇用対応力の強化、公務員試験対策の必要性を提案する。
キーワード
図書館司書資格、非正規雇用、キャリア形成、モチベーション、大学支援策
ページ
91-96
本文を見る
相良奈津|東北ブロックコンテスト2024の学生指導と2024ジャパンケーキショー東京への作品出品
著者
相良奈津
題名
東北ブロックコンテスト2024の学生指導と2024ジャパンケーキショー東京への作品出品
著者(ローマ字)
SAGARA Natsu
題名(英語)
Guidance for students in the Tohoku Block Contest 2024 and submission of works to the 2024 Japan Cake Show Tokyo
要約
本実践発表は、東北ブロックコンテスト2024の学生指導と、2024ジャパンケーキショー東京への自身の作品出品についての記述であり、実践を通じて学生指導を行うことで今後の教育に役立てていくことを目的とした。その結果、学生の「やりたいこと」と「できること」を体験させ自覚させるためには膨大な時間を要することが必要であると感じた。
キーワード
ジャパンケーキショー東京、東北ブロックコンテスト、マジパン細工、コンテスト
ページ
97-100
本文を見る
佐々木貴弘、佐藤万利子、君島智子|保育内容B授業実践報告
著者
佐々木貴弘、佐藤万利子、君島智子
題名
保育内容B授業実践報告
著者(ローマ字)
SASAKI Takahiro, SATO Mariko, KIMIJIMA Tomoko
題名(英語)
Childcare practices that foster "expression and communication"
要約
保育内容Bにおいて実践した「表現と伝えあい」を育む保育実践について、活動内容や活動結果をもとに今後の課題を検討した。授業では、「ボディパーカッション」、「素話」、「太鼓を使った表現」、「劇遊び」などの実践を取り上げたが、特に、子どもと共に作り上げる劇遊びなどの表現活動の中では、共に気持ちを伝え合い、心を通わせ創り上げた体験をしたことが示唆された。卒業後も現場で、子どもの表現力を育むための関わり方や指導方法を模索し、各々の実践に向けた礎となればと考えている。
ページ
101-106
本文を見る
佐藤万利子|子どもの感性を育むために習得してほしい表現活動の実践
著者
佐藤万利子
題名
子どもの感性を育むために習得してほしい表現活動の実践
著者(ローマ字)
SATO Mariko
題名(英語)
Practicing musical expression to develop children's sensibilities
要約
子どもの豊かな感性と表現を育むためには学生自身にも豊かな感性を獲得することが求められる。近年入学してくる本学の学生には、ピアノ初心者が6割近くおり、子どもの歌や童謡に触れる機会が少なかったとの意見が多く聞かれ、授業の中では多くの童謡や子どもの歌を教材として取り上げるように努めている。子どもの感性を育むための表現、そのために習得してほしい表現活動が体験できるように授業内容を検討し、体験する機会を設けてその振り返りアンケートから内容を更新していくことが必要だと思われる。音楽教育によって育まれる感性は、学習効果も向上すると考えられる。子どもの感性を育むためには、学生自身が感動し楽しめる音楽体験を、本学在学中に積み重ねることが必要で、その機会を提供したいと考える。
キーワード
音楽表現の体験、感性の育成、音楽教育
ページ
107-112
本文を見る
高間章|放課後等デイサービスにおける発達障害児への運動療育に関する実践報告
著者
高間章
題名
放課後等デイサービスにおける発達障害児への運動療育に関する実践報告
著者(ローマ字)
TAKAMA Akira
題名(英語)
A study on developmental support through exercise for children with developmental disorders.
要約
放課後等デイサービスは2012年に児童福祉法に位置づけられた児童通所支援事業で、創作活動や余暇活動などのプログラムを通じて、日常生活動作の習得や集団生活への適応に向けた支援を行うものである。本稿では筆者がこれまでに放課後等デイサービスで実施してきた運動指導内容を➀他者とのコミュニケーションを含んだプログラム、➁協調運動を含んだプログラム、➂その両方の要素を含んだプログラムに分類し、期待される効果を加えて紹介した。また、運動効果の検証のひとつになる全身反応時間の測定をスポーツクラブに所属する児童と放課後等デイサービスに通所する児童に実施し、スポーツクラブ児童は各種の反応時間が短く、選択反応時間の誤りも少ない傾向がみられた。
キーワード
運動療育、発達支援、発達障害
ページ
113-118
本文を見る
宮本 美和子、中島 恵、山本 信|令和5年度保育内容C(あそびの文化と伝承)授業実践報告:「身近な素材を使った遊びの工夫」を通した学習成果に関する調査
著者
宮本 美和子、中島 恵、山本 信
題名
令和5年度保育内容C(あそびの文化と伝承)授業実践報告:「身近な素材を使った遊びの工夫」を通した学習成果に関する調査
著者(ローマ字)
MIYAMOTO Miwako, NAKAJIMA Megumi, YAMAMOTO Makoto
題名(英語)
Report on the Lesson of “Contents of Early Childhood Ecudcation and Care-C”ーthe Culture and Tradition of Play: A study of Learning Outcomes through “Creating Play Ideas Using Familiar Materials.”
要約
本報告では、保育者養成校での遊びと文化の伝承を目的に「身近な素材を使った遊びの工夫」をテーマに展開した授業の受講生29名の身近な素材を使った遊びの良さについての自由記述を分析した。
キーワード
保育者養成、遊び、学習成果
ページ
119-124
本文を見る