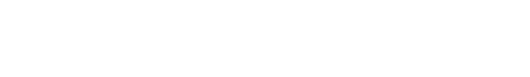本学の建学の精神は、仏教の教えに基づく教育であり、具体的には自他を大切にし慈しむ「慈悲」の心、支えあい協力し合う「和」の心を身につけ、「智慧」を学ぶ人間教育を通して、地域社会に貢献する有能な人材を育てることです。
本学の特徴としては、仏教系の大学の多くがいずれかの宗派に属しているのに対し、本学はいずれの宗派にも属さず、仏教の開祖釈尊の「慈悲」と「智慧」、聖徳太子の「以和為貴」(和を以て貴しと為す)の教えに基づく教育を教育の理念としていることです。
教育目的・教育目標
各学科の教育目的・教育目標は以下の通りです。
キャリア開発総合学科
建学の精神に基づく人間教育を基本理念とし、開かれた社会性、将来につながる専門性の育成を目的とする。教育目標は次のとおりです。
- 地域社会に貢献するための豊かな人間性と社会性を備えた人間を育成する。
社会人としての教養を深める共通教育科目と、学科の多彩な専門領域を追究する専門教育科目をあわせて学習することにより、関心の幅を広げ、地域社会の多様な分野において活躍できる知識と技能を習得する。 - キャリア教育を通して、職業人としての意識と能力を高める。
社会人としてのマナーやコミュニケーション能力を高める一方、進路の目標に沿った各種の資格・検定への挑戦や、学科が推進する行事および地域交流活動への参加などを通して、職業人としての資質向上を図る。
保育学科
本学の教育理念に基づく円満な人格を育成し、保育に携わる者としてふさわしい専門性や資質を備えた保育者を養成することを目的としています。教育目標は次のとおりです。
- 豊かな人間性と幅広い教養を身につける(心)
乳幼児期から児童・青年期までの深い子ども理解に基づき、子どもの人格形成に携わる保育者としての自覚を持ち、豊かな人間性と広い教養を身につけ、保育者としてふさわしい態度や資質の向上を図る。 - 専門的な知識を身につける(知識)
子どもの発達や社会的適応を援助、支援するための専門的理論や知識を身につけ、子どもの姿と環境の観点から援助および支援のあり方等について広い視野で理解し、正しく判断する知性を養う。 - 基礎的な技能を身につける(技能)
子どもの主体的な活動を援助するために必要な幅広い確かな基礎的技能を身につけ、指導力を培うと共に、自ら保育を創造していくための力を養う。